【株式会社Synergy Career】
岡本恵典社長インタビュー
岡本恵典社長インタビュー
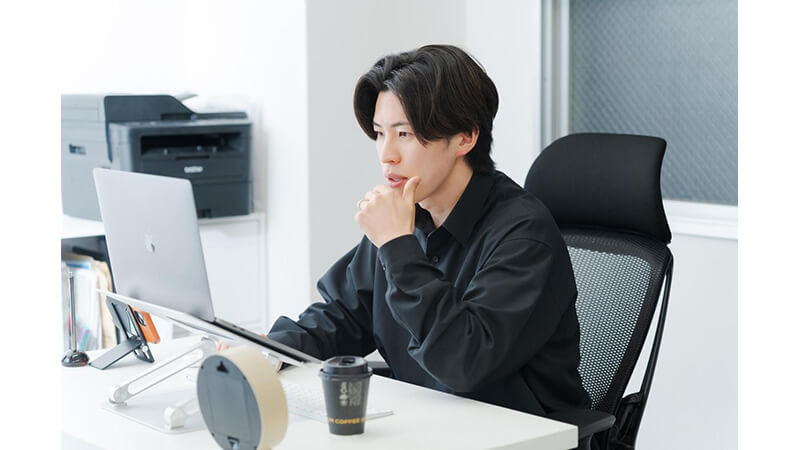
【株式会社Synergy Career】
岡本恵典社長インタビュー
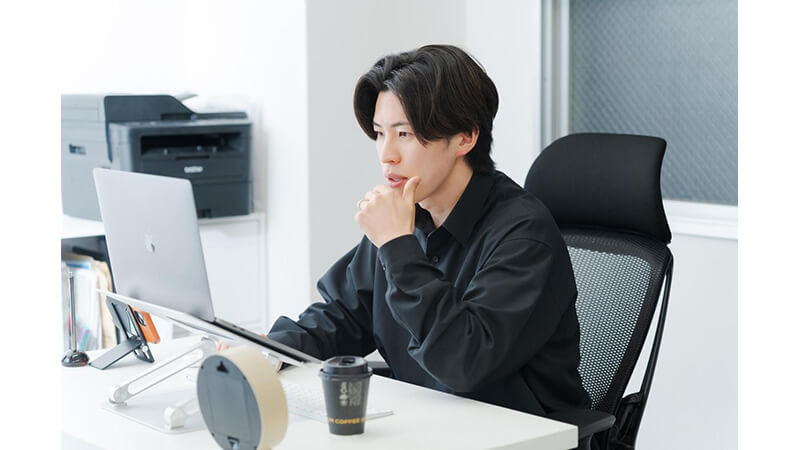
岡本恵典氏略歴
・大阪府立大学大学院 理学系研究科 分子科学専攻 有機合成化学研究室 卒業(2015卒)
・株式会社イノベーション(東証マザーズ:3970)に新卒入社
・自身の就活経験に課題を感じ、WEBサイト「就活の教科書」を立ち上げ
・自己分析の書籍「ワークと自分史が効く! 納得の自己分析」を出版
・朝日新聞、TBSラジオ、ベンチャー通信など、多数のメディアに掲載
・マイナビニュース、Infra、JobSpringなど、多数のメディアへ記事寄稿
・合同説明会、就活セミナーなど、多数のイベントの登壇
・国家資格キャリアコンサルタントを取得
・就活支援として、OB訪問アプリ「Matcher」でレビュー数100超
私が就活支援の領域に関心を持つようになったのは、「就活には、もっと良い形があるはずだ」と感じたことが出発点です。
当時の就職活動では、学生自身の意思や得意分野といった本質的な要素よりも、大人の支援があるかどうかで結果が左右される傾向がありました。面接対策を徹底的に行ってもらえる環境がある人が優位に立ち、そうでない人はどれだけ真剣に考えても届かないという構造があったように思います。
もちろん、支援を受けること自体は悪いことではありません。しかし、その情報やノウハウにアクセスできるかどうかが、個人の力とは関係のないところで不利や有利を分けてしまう。その状況は公平ではないと感じました。
だからこそ、就活に関する正確で本質的な情報を、誰もが等しく手に入れられるようにしたいと考えました。すべての就活生が同じ情報を持ち、公平な立場で選考に臨める環境を整えること。それは就活生にとって健全であるだけでなく、企業側にとっても本当に必要な人材と出会いやすくなるという利点があります。
こうした課題意識のもと、就活メディアの立ち上げに至りました。
当初は「情報が足りない」という課題意識が出発点でしたが、現在では「情報が多すぎる」ことによる混乱も顕著です。インターネット上にはさまざまな情報が氾濫しており、就活生がどの情報を信じるべきか判断に迷う場面が増えています。
そのような状況の中で、私たちは客観性のある正確な情報を厳選し、体系的に提供することを使命としています。情報の漏れがなく、信頼できる内容をまとめて提供することで、「このサイトさえ見ておけば大丈夫だ」と思ってもらえる存在を目指しました。
この理念を体現するために、「就活の教科書」という名前を冠し、メディアとして再構築し、事業として本格的にスタートしたのが原点です。
学生時代は、理系の学部に所属し、大学院まで進学していました。アルツハイマー治療薬として期待される化合物の全合成に取り組んでいました。粛々と研究に取り組む、いわゆる典型的な理系の研究生活を送っていたと思います。
課外活動としては、大学祭の実行委員会に所属していました。そこでは、複数の模擬店を統括し、出店配置の決定、注意事項の伝達、物品準備、当日の運営補助といった実務面を担当しました。また、国際交流サークルにも所属しており、留学生と交流を図る機会もありました。
理系の勉強は決して嫌いではありませんでしたが、それ以外の分野にも、社会の役に立つ手段が多くあると感じるようになりました。課外活動などを通じて、理系に限定されない広い領域で価値を生み出せる可能性に惹かれ、最終的には文系就職の道を選びました。
新卒で入社したのはIT系の企業でした。法人営業として、当時注目されていたマーケティングオートメーションツールの新規開拓を担当しました。展示会での名刺交換、テレアポ、訪問・提案・契約といった一連の営業活動をしていました。
営業活動を通して感じたのは、WebやITの技術を活用すれば、より効率的かつ体系的な営業活動が可能になるということです。再現性や効果の面でも優れた方法があるのではないかと感じ、そうした思考が徐々に強くなっていきました。
その経験を踏まえて、最終的にメディアの事業を立ち上げるに至りました。これが、現在に至るまでの私のキャリアの歩みです。
私自身、「出会いを生かす」ということを常に大切にしています。
たとえば、これまで会ったことのない人に会ってみる、やったことのないことに挑戦してみる、あるいは興味がなかった分野にも一度踏み込んでみる、そういった姿勢を意識してきました。大きなことではなく、日常の中の些細な挑戦でも構わない。そういった小さな行動の中に、新しい発見があると考えています。
その発見とは、情報としての気づきであったり、人との新しい出会いであったりします。そうした偶然の出会いや学びが、自分の世界を広げてくれる。その意味で、新しいことを受け入れる柔軟さを大切にしてきました。
国際交流サークルへの参加は印象深い経験です。もともとは外国人に対して距離を感じていた部分もありましたが、実際に関わってみると偏見がなくなり、多くの友人ができました。むしろ、自分がどれだけ狭い価値観の中にいたのかを思い知らされました。
こうして新しいことに挑戦する中で、自然と自分の視野が広がり、価値観が変わっていった実感があります。継続的に社会に価値を届けるためには、やはりビジネスとしての仕組みが必要であると理解したのです。
このように、すべてがつながっていく感覚があります。偶然の出会いを「偶然」のままにせず、自分から飛び込んでいく姿勢が、その後の大きな意味を持つことがある。だからこそ、私は偶然を大切にし、意図的に新しい場へと足を運ぶことを心がけています。
当社では、主に大学生をターゲットとした就職活動に関するWebメディア(就活の教科書:https://reashu.com/ )を運営しています。
就職活動の過程で多くの学生が直面する困りごと、たとえば面接対策やエントリーシートの書き方、自己分析の方法といったテーマに対して、実践的かつ網羅的な情報を提供しています。
現在、サイト上にはすでに約2,500本の記事を公開しており、学生の皆さんが必要とする情報に幅広く対応できる構成となっています。
サービス全体としては、累計5,000万回以上のアクセスを記録しており、多くの就活生にご活用いただいています。
このように、「就活の教科書」は、就職活動に取り組む大学生にとって、信頼できる情報基盤となることを目指して運営を続けています。
「就活の教科書」の大きな特徴として、現役の大学生や内定者のメンバーが運営に関わっている点が挙げられます。彼らと一緒にコンテンツを制作する体制をとっていることで、学生目線での情報提供が可能になります。
大学生が編集や執筆に携わることで、就活生が実際に今、どのような悩みを抱え、どのようなテーマに関心を持っているのかを、より的確に把握することができます。また、同世代だからこそ伝えられる言葉選びや構成によって、読者にとって違和感のない、自然に響く表現が可能になります。
さらに、当社では学生編集部が取材業務にも携わっています。企業の人事担当者や大学教授の方々へのインタビューを、学生自らが行っています。これは、学生が「今まさに知りたいこと」をダイレクトに尋ねられるという点で、他のメディアにはない強みです。
結果として、学生の関心に寄り添ったインタビュー記事を制作することができ、それが他社には実現しにくい独自性あるコンテンツへとつながっています。
記事の執筆は学生が担当していますが、内容の確認や最終チェックはキャリアコンサルタントである私が行っており、情報の正確性を担保しています。
こうした学生主体の編集体制こそが、「就活の教科書」における最も大きな差別化要因であると考えています。
メディア運営における基本的な方針として、「就活の教科書」では、就職活動に関する情報を教科書のように体系的にまとめて提供することを目指しています。
就活生が信頼できる情報源として活用できるよう、正確性と客観性を重視し、可能な限り網羅的な情報を掲載するよう努めています。
たとえば、エントリーシートの書き方や面接対策といった基本的な情報はもちろんのこと、就活において見落とされがちな点や最新の傾向まで含めて、読者にとって過不足のない内容になるよう編集方針を定めています。
こうした方針は、他のメディアとの差別化要因であると同時に、私たち自身が最もこだわっているポイントでもあります。
単なる体験談や感覚的なアドバイスにとどまらず、誰が見ても納得できるような、信頼性の高い情報を一貫して提供する姿勢を貫いています。

「就活の教科書」は、情報が溢れる現代において、あえて情報を選び取り、就活生にとって本当に必要な情報を整理して提供することをコンセプトとしています。
私たちは、この理念に強い意義を感じており、今後さらにその情報の「使いやすさ」や「探しやすさ」を高めていきたいと考えています。就活生が求める情報にすぐにたどり着ける構造を整備し、それらの情報を通して、自らの就活をより良くできるような仕組みをつくっていく。それが、私たちが目指している方向性です。
最終的には、「就活中にわからないことがあれば、まず“就活の教科書”を見ればいい」と学生に思ってもらえる存在を目指しています。エントリーシートの書き方、面接対策、自己分析の方法、業界研究など、就活に必要なノウハウがすべて網羅されている、いわば“就活生の必須ツール”となることが、私たちのビジョンです。
単なる情報提供にとどまらず、学生が自らの行動や選択に自信を持てるようになるための支援を行う。そうした価値のあるメディアを築き上げていきたいと考えています。
ご縁があり、出版社の方からお声がけをいただいたことをきっかけに、書籍を出版させていただきました。
この本では、「就活で本当に役立つ自己分析って何だろう?」という問いに向き合いながら、その答えとなるようなフレームで自己分析をまとめました。
多くの学生が行っている自己分析は、分析すること自体が目的化してしまっているように感じています。そもそも、何のために自己分析をするのかが不明確なまま、設問に答えるだけで満足してしまうケースが非常に多い。時間をかけて取り組んでも、「結局、自分は何がしたいのか分からない」という状態になってしまうのです。
このような形で自己分析を終えてしまうと、「なぜこの会社を受けたのか」と聞かれたときに答えられず、面接の場でも一貫性を持った回答ができなくなってしまう。それでは、自己分析が就活の武器にはなりません。
そこで私は、自己分析の目的を明確に限定しました。就活において必要な自己分析は、突き詰めれば次の二つだけで十分だと考えています。
1.自分はどのような会社に行くべきなのか
2.その会社で自分はどのように活躍できるのか
この二つに答えられるようにすれば、業界や企業規模、職種の選定ができ、志望動機にも一貫性が生まれます。また、「御社でこういう形で貢献できます」と自信を持って伝えられるようになります。
逆に言えば、この二つ以外の自己分析は、趣味として楽しむ分には構いませんが、就活においては必須ではないと考えています。「幸せとは何か」「人生の意味とは」といった問いに没入してしまうと、自己分析が哲学的思索になってしまい、現実的な判断材料としての機能を果たさなくなります。
したがって、私はこの本の中で「就活」という範囲に目的を限定し、就活に必要な情報だけを導き出せる自己分析のフレームを設計しました。就活生が迷わず、本当に必要な問いにだけ向き合えるようにすること。それが本書のコンセプトであり、執筆に込めた私の意図です。
「就活の教科書」を一緒に盛り上げてくれるメンバーを募集中です!
https://reashu.com/recruitment/
私たちは、自分で自分の人生を良くしていける人が増えてほしいと強く思っています。
納得のいく人生を、自らの意思でつくっていくことができれば、その人の人生は間違いなく幸せだと言える。なぜなら、自分自身で良くできるわけですから。
一方で、自分の人生の舵取りを他人や環境に委ねてしまっている人も少なくありません。たとえば、自分ではどうにもならない運や偶然に期待していたり、大きな変化が起きないと状況が変わらないと思い込んでいたりする。
そういった人たちが、少しずつでも「自分の力で状況を動かせる」という実感を持てるようになることが大切だと考えています。
そのために、当社の中で仕事を通じて、その力を体得してもらいたいと思っています。
たとえば、自分に与えられた職種や役割の中で、まずは自ら目標を設定する。次に、その目標達成を妨げる要因を特定し、解決策を考える。
それを実行に移し、進捗を管理しながら必要に応じて改善を重ねていく。この一連のプロセスを、自分で考え、実行し、振り返ることができるようになる。これが習慣になれば、仕事でも成果が出るようになりますし、それはそのまま人生そのものを良くしていく力にもつながると考えています。
私たちは、仕事と人生がつながっていると本気で思っています。
だからこそ、日々の業務においても、「どう思う?」「どうしたい?」「仮説は?」「今の課題は何だと思う?」といった問いかけを通じて、メンバー自身に考えてもらうようにしています。
その中で、自らの思考で答えを導き出す力を磨いていってほしい。
そして、最終的には「自分の人生を自分で決められる人」になってほしいと願っています。
反対に、すべてを社長や上司に委ねて、「言われた通りに動きます」といったスタンスでは、当社の文化とは合いません。なぜなら、私たちの組織では常に意見を求められるし、自分の意志を問われる場面が多くあるからです。
ですから、意思を持ち、自ら考え、自分の人生を主体的に切り拓いていける人こそ、私たちの組織において活躍できる人材だと考えています。

企業名 : 株式会社Synergy Career
代表者 : 岡本 恵典
所在地 : 大阪府大阪市北区梅田
設立 : 2020年6月
従業員数: 15名
事業内容
・WEBメディアの運営
・企業への採用支援
・学生への就活支援